COLUMN印刷ラボ
打ち合わせ方法
入稿後のデータ修正、どこで直すのが正解?

執筆 2025/10/28 福富康一(福ちゃん)
印刷トラブルを防ぐための“修正ワークフロー”を考えてみましょう!
こんにちは。
大洋印刷の福富です。今日は「入稿したあとにデータを修正したくなったら、どうすればいいのか?」というテーマでお話しします。
この話、実は印刷現場ではとてもよくあるんです。
入稿した後、念の為の校正(念校)を確認している時に
「あ、ここ文字が違う」
「やっぱり色味を変えたい」
といった修正が発生するのは、無い方が良いのですが、やはり人のすることですので発生することもありますよね。
でも、その「入稿後のちょっとした修正」が、思わぬトラブルの火種になることがあります。
「先祖返り」という怖い現象
印刷会社の現場では「先祖返り」という言葉があります。
一度修正して完成したはずのデータなのに、次の増刷や姉妹品のデザインを作るときに、以前のミスが“復活”してしまうという現象です。
たとえばこんなケースです。
あるパッケージの誤字を、印刷会社が社内で修正して納品しました。
印刷物は問題なく仕上がり、お客様もデザイナーも一安心。
ところが数ヶ月後、「同じシリーズの新商品を作りたい」との企画が始まりました。
デザイナーさんが手元の元データを流用して新しい箱を作った。
すると、あの時修正したはずの誤字が…元に戻っていた。
つまり、「印刷会社が直したデータ」と「デザイナーが持っている元データ」が違うまま進んでしまったのです。
これが、印刷現場で最も怖い“先祖返り”です。
データ修正の鉄則①:修正は“元データ側”で行う
印刷会社で一時的にデータを直すことは、納期が迫っている時などやむを得ない場合もあります。
でも原則として、修正はデザイナーさんが持っている元データで行うのが基本です。
なぜかというと、印刷会社側の修正は「出力用データの整合性」を取るためのもので、
長期的なデータ管理の責任は基本的にデザイナー側(または発注元)にあります。
印刷会社は印刷を安全に進めるための“一時的な修正”を行うことはあっても、
それを元データとして引き継ぐ立場にはありません。
ですから、もし印刷会社で修正を行った場合は、
その修正内容を必ずデザイナーさんに伝え、元データへ反映してもらう必要があります。
データ修正の鉄則②:部分データでの再入稿が理想
もう一つ、現場でよくある誤解があります。
修正をしたいときに「全データをもう一度入稿しますね」と言われるケースです。
一見丁寧な対応に見えますが、実はこれは非効率的で危険です。
印刷会社では、入稿後に面付けや色分解(分版)といった工程が進んでおり、
全データを差し替えると、その工程をすべてやり直す必要が出てしまうのです。
その結果、再チェック・再出力・再面付けと、時間もコストも余分にかかります。
データチェックも人がすること。
1回目の入稿では気がついたことでも、2回目では見落としてしまう。そんなトラブルも考えられます。
もし修正箇所が1ヶ所や数文字だけであれば、その部分だけを修正データとして入稿してもらう方がスムーズです。
印刷会社にとっても「どこが変わったのか」が明確になり、
データの差し替えも確実かつ安全に行えます。
ワークフローを整えることで防げるミス
印刷のトラブルの多くは、実は“人の勘違い”や“伝達漏れ”から起こります。
特にデータの修正に関しては、
- 誰が修正をしたのか
- どのデータが最新なのか
- どこが変更になったのか
この3点が共有できていないと、あとで混乱が起こります。
私たち大洋印刷では、こうしたトラブルを防ぐために、
案件ごとに「改訂履歴」をEvernoteやkintoneで管理しています。
また、デザイナー様にも「修正後の最終データ」を必ず保管していただくようお願いしています。
印刷会社の“善意の修正”がリスクになることも
印刷現場では、データの不備を見つけた際に「これなら自分たちで直した方が早い」と思ってしまうことがあります。
しかし、その“善意の修正”が後にトラブルを生むこともあるのです。
たとえば、文字のアウトライン忘れ・画像のリンク切れ・特色指定のミスなど。
印刷会社の判断で一時的に整えたとしても、デザイナーさん側が気づかないまま次の案件に流用してしまう可能性があります。
その結果、ブランド全体の統一感を欠いたり、印刷仕様がズレたりすることもあります。
ですから、印刷会社とデザイナーは“修正をどちらが行うか”を明確に決めておくことがとても大切です。
修正のルールを明確にすることが「品質」を守る
印刷は「人」と「データ」と「工程」が連動して初めて成り立ちます。
どんなに技術が進んでも、修正ルールが曖昧なままでは品質は安定しません。
データ修正のたびに、
- 誰がどこを直すのか
- どのデータが最新版なのか
を確認し合う。
たったそれだけで、後のトラブルは大きく減らせます。
印刷会社もデザイナーも、そして発注元も、
お互いの立場を理解しながら「正しい修正フロー」を共有しておく。
それが、“失敗しない紙箱づくり”への第一歩です。
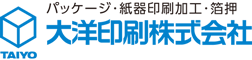
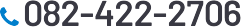



 オンラインショップ
オンラインショップ

 BACK
BACK 一覧に戻る
一覧に戻る

